インフォームド・コンセントと説明書・同意書
- heiwamed0001
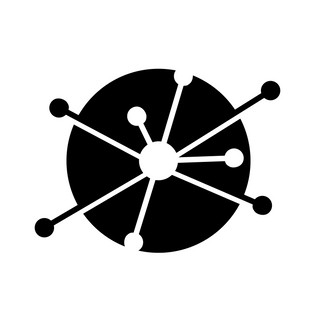
- 2025年1月10日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年2月25日
交雄会新さっぽろ病院 消化器内科 北澤 俊治
インフォームド・コンセントとは「医師等が医療を提供するに当たり適切な説明を行い、患者が理解し同意することをいう」と定義されています(2013年精神保健福祉法に基づく厚生労働大臣の指針)。
当院では様々な医療行為に対して説明および同意取得を行っておりますが、内視鏡診療に関するすべての検査および治療(鎮静・鎮痛の前処置等も含む)についても、十分な説明を行い、同意を取得することを日常的に心がけております。内視鏡診療におけるインフォームド・コンセントに含まれる内容としては①病名あるいは症状から疑われる疾患名、②内視鏡検査・治療の目的、方法、必要性、期待できる効果など、③予想される危険性(偶発症)の内容とその対処法、偶発症が発生する頻度、④代替検査や代替治療の可能性について、⑤患者がその医療行為を受け入れない場合に予想される事態、以上の項目が挙げられます。
説明および同意取得に関して注意すべき点として、医師が十分な説明を行ったと考えていても、患者さんや家族は十分に説明を理解できていないケースも少なくありません。従って、説明と同意は、口頭での説明と同時にその内容を文書で明示し、確認できるようにしております。また説明で注意する点として、専門用語をできる限り避けて、患者さんにわかりやすい表現を用いることも必要です。診療科の医師だけではなく、診療科以外の医師や医師以外のスタッフが読んでもわかるように記載・説明するようにしております。
最近「Shared decision making」という言葉が注目されています。これは「共有意思決定」や「協働的意思決定」とよばれており、患者さんにとって最も大切なことに沿って、医療者と患者さんが協働して、患者さんにとって最善の医療上の決定に至るコミュニケーションのプロセスを意味します。インフォームド・コンセントは、医療者が勧める最善と思われる治療に対し、適切な情報開示を行ったうえでなされる患者さんの自発的な受託ですが、「Shared decision making」では患者さんにとって何が最適なのかを医療従事者と患者さんがともに考えるものであり、患者さんの望む方針が医学的に最善なものであるとは限りません。選択肢が複数あり、どちらがよいのか明らかでない場合に「Shared decision making」が特に重要とされています。
インフォームド・コンセントの重要性について広く認知されるようになりましたが、その理念が十分に理解されているかというと、必ずしもそうではありません。医療従事者の観点からは、責任回避を重視して形式的な説明を行い、患者さんに治療選択を迫ってしまうケースもありえましょう。また、患者さんの観点からは、患者さんの権利を主張するケースや、専門的な話はわからないとはじめから説明を理解しようとせずに医師側に治療選択を委ねるケースも少なくないのではと思います。インフォームド・コンセントの目標は、懇切丁寧な説明を受けたいと望む患者さんと、十分な説明を行うことが医療提供の重要な要素であるとの認識をもつ医療従事者が協力し合う医療環境を築くことです。こうした理念を十分に理解し、良好な医師―患者関係を構築するために、当院スタッフ一丸となって努力してまいります。



